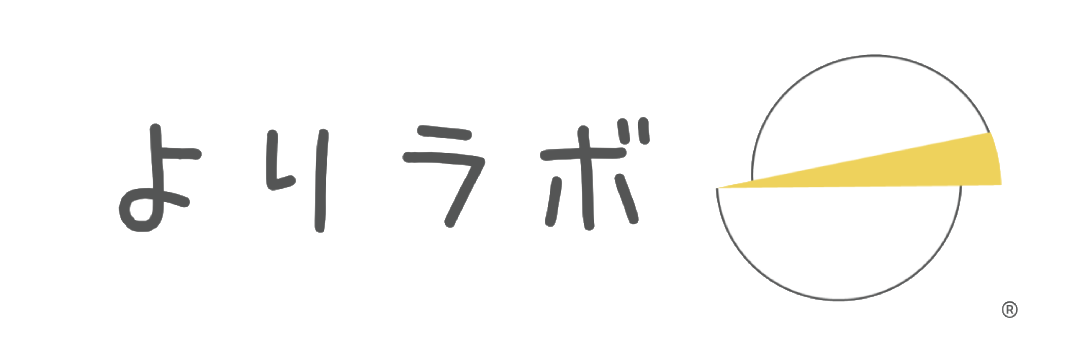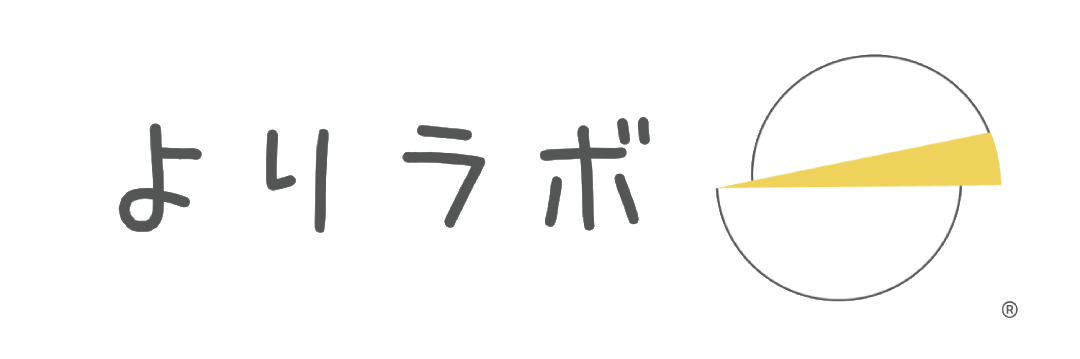2025/04/24 18:00

はじめに
ご飯 → おかず → 汁物 → ご飯 →・・・。
この“回遊ルート”が作る、見えない三角形。
それこそが、かつて学校給食で教わった「三角食べ(3点食べ)」です。
本レポートでは、誕生の背景からメリット・デメリットについて解説します。
誕生の背景
1970年代の学校給食で「完食」と「牛乳消費」を促すために導入されたのがきっかけ。
2007年版『食に関する指導の手引』には“交互に食べよう”の文言があったものの、2019年改訂版で削除。
つまり、今は“必修”ではなくなりました。
「三角食べは伝統だから守るべき」というよりは、目的に合わせて選ぶ食べ方の1つになっています。
三角食べのメリット
全部まんべんなく減る!
好き嫌いで残る“ばっかり食べ”を防ぎ、栄養バランスが整う。
口の中がミニ和食ダイニング
ごはん&おかずを同時に噛む“口内調味”が味覚を鍛え、咀嚼回数もアップ。
食文化体験
「ご飯を中心におかずで味を調える」という和食文化を体感できる。
三角食べのデメリット
血糖値スパイク
主食(ご飯)を先に口へ → 血糖値のピークが高くなりやすい。
早飲み・早食い
汁物が“流し込み”を助長し、咀嚼不足に。
濃い味依存
ごはんに合わせるため、おかずの塩分が濃くなりがち。
三角食べは、こんな人におすすめ
・好き嫌いが多いお子さん
・食事のペースが速すぎる人
・日本の食文化を体験したい家庭
まとめ
三角食べは“楽しく完食できる”食育メソッドとして優秀ですが、いくつかの観点では工夫が必要です。
目的に合わせて食べ方を変え、家族みんなでおいしく健康的な食事を楽しみましょう!
参考文献
文部科学省『食に関する指導の手引-第二次改訂版-』(平成31年3月)
佐藤雅子・綾部園子(2024).学校給食における偏食や好き嫌いについての指導の変遷ー戦後の学校教育への位置づけー.日本家政学会誌, 75(3), 119–131.