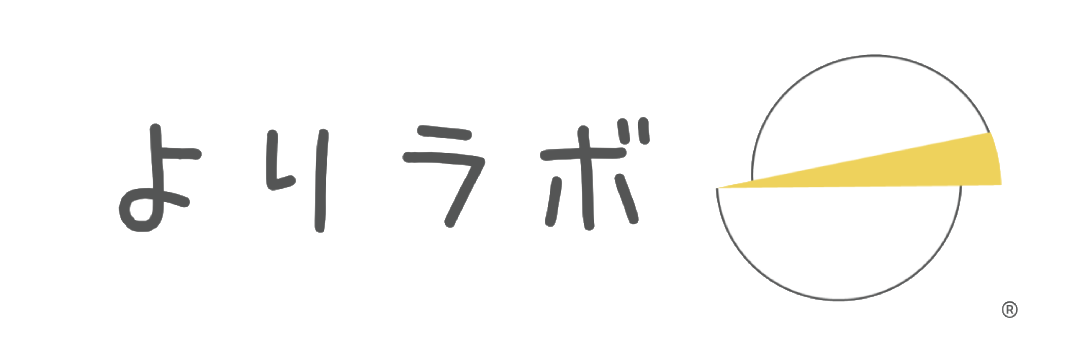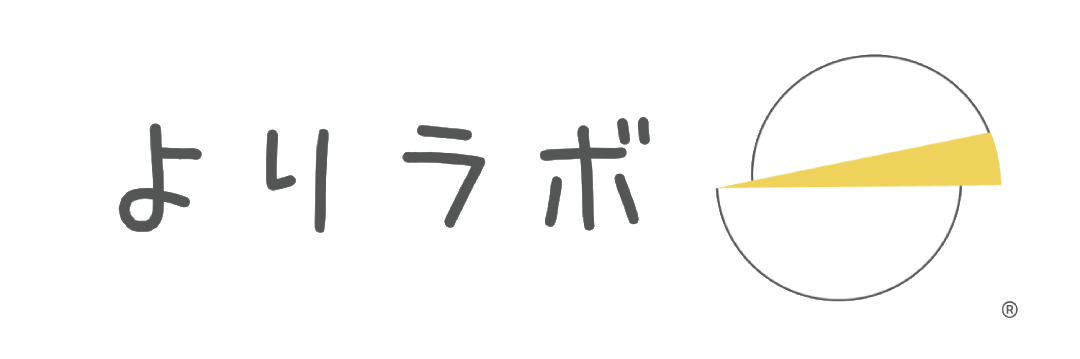2025/11/20 21:00

はじめに
ナプキンの歴史は、食べやすさの歴史。
フォークやテーブルマナーと同じく、ナプキンも衛生・身だしなみ・合図を支える主役。
じつはそのルーツは古く、古代の「拭く」工夫にまでさかのぼります。
古代の工夫:パンくず→リネン
古代ギリシアでは、パンの中身(apomagdalia)で指を拭いたという記述(アリストファネス『騎士』)があり、いわば“食べられるナプキン”でした。
ローマでは、mappa(マッパ)やmantele(マンテレ)と呼ばれる布が使われ、個人が持参する小布(mappa)と大判の布(mantele)が併用されました。
中世~ルネサンス:共同タオルから“個人のナプキン”へ
中世ヨーロッパでは、テーブルクロスや共用の拭き布が機能を担う場面が多くありました。
ルネサンス期にはテーブルリネン文化が洗練され、ナプキン=個人用の布が定着していきます。
17世紀のブーム:折り紙的“ナプキン折り”の誕生
1639年には、イタリア・パドヴァで活動したMatthia Giegerの著作にナプキン折りの体系的マニュアルが登場。
宮廷や上流階級の食卓では、彫刻のように折り上げた「魅せるナプキン」が流行しました。
18~19世紀:近代レストラン文化と量産が後押し
サービス・ア・ラ・リュス(料理を順番に出す様式)や近代レストラン文化の普及で、ナプキン=所作と合図として標準化。
産業革命による織物・加工の発達は、品質の安定と普及をさらに加速させました。
紙ナプキンの登場:東から西へ
紙の発明(中国、1世紀頃)ののち、中国では茶の供出に小さな紙片(“chih pha”)を折って用いる慣習があり、これが紙ナプキンの源流とされます。
西洋で紙ナプキン産業が立ち上がるのは19世紀末。
日本の装飾紙ナプキンがイギリスの会社を通じて紹介され、ブランド印刷入りの“記念ナプキン”がトレンドに。
20世紀に入ると一般家庭や外食で広く定着しました。
よくある“都市伝説”
「レオナルド・ダ・ヴィンチがナプキンを発明した」という話は有名ですが、近代のジョーク本が由来の作り話とされています。
面白い逸話ですが、史実としては受け入れられていません。
まとめ:ナプキンは“静かな技術”
パンくず→リネン→折り紙的演出→紙の量産。
ナプキンは時代ごとの課題(衛生・所作・合図)を解くために進化してきました。
次にひざ上でナプキンを広げるとき、ローマのmappaや中国の紙文化、そして近代のテーブルマナーが一本の線でつながっていることを、少しだけ思い出してみてください。